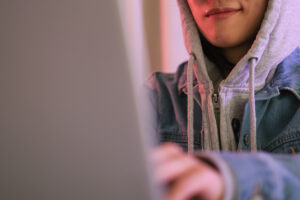ストックフォトと意匠権
この写真はストックフォトとして販売できるでしょうか?

突然ですが、質問です。
この写真(ペリカンというメーカーのメカニカルペンシル)はストックフォトとして販売できるでしょうか?
撮影者は私自身(monzenmachi)なので、写真自体の著作権はmonzenmachiにあります。
被写体の権利はどうでしょう?
メーカーのロゴは写っていないので、ロゴマークに付随する著作権と商標権は発生していません。
ここで問題となるのが、メカニカルペンシル全体の形状や細部のデザインにどのような権利が発生するかということです。
この記事では、ストックフォトと意匠権の関係、つまり意匠登録されている商品を写真に撮ってストックフォトとして販売してもよいか?ということについて考えてみたいと思います。
肖像権や著作権、商標権についてはフォトグラファーの間では比較的よく知られていると思います。しかし、意匠権については私も含め多くのフォトグラファーの間で大まかにしか理解できていない点もあると思いますので、フォトグラファーとしての立場から気になる点を中心に、意匠権とストックフォトの関係について調べてみました。
なお、この記事は日々の撮影業務の中で感じた法律に関する疑問を、個人的な関心にしたがって書いています。詳細で正確な法的な知識を必要とされる場合には、法律の専門家にご相談ください。
意匠権とは何か?
工業製品と著作権
このメカニカルペンシルのような大量生産される工業製品のデザインは、著作権法では保護されません。
Tシャツなど量産される衣服に描かれたデザインも著作権法ではほとんどの場合保護されません。
著作権法(第2条1項1号)は、「思想又は感情を創作的に表現した」、「文芸、学術、美術又は音楽」の範疇に属する創作物を保護しています。工業製品のデザインも著作権法が保護する「美術」の範疇に入るようにもみえます。
しかし、著作権法が想定している「美術」とは、絵画や書や彫刻など、もっぱら鑑賞を目的とした創作物=「純粋美術」のことです。工業製品のデザインのような「応用美術」に関しては、著作権法ではなく、意匠法で保護するというのが通常です。
ただし近年では、Tシャツのような実用品であっても、独創性が認められる場合にはTシャツにプリントされたイラストや写真を著作物として分離できるという「分離可能説」に基づいて、(平成26年)Tシャツに印刷されたイラストが著作物として保護された判例(参照)もあるので、今後は意匠権と著作権の関係も変わってくる可能性もあります。その一方で、(平成27年の)別の訴訟の判決では、シャツの「刺繍」や「布地(テキスタイル)」の絵柄の著作物性が否定されるなど、過渡期にあるようです(同参照)。
そうした変化はみられつつも、応用美術に属する大部分の工業製品のデザインは、現状では著作権法ではなく、意匠法によって保護されることになります。
意匠法の目的
意匠法の目的は(同法第1条によると)「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」です。
そして、意匠法で保護の対象となるのは、「物品、建築物、および画像」の「意匠」(いわゆるデザインのこと)です。※なお、ここでいう「画像」とは、電子機器類のディスプレイ等に表示される画像のことで、絵画のような著作権法で保護される画像のことではありません。
意匠法は、物品等の意匠を法的に保護し、意匠の創作者が自分の意匠を「専有」して、そこから業としての利益を得る権利を保障しています。つまり、同法第23条で意匠権者が、「業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」ことが明示されています。
意匠を保護し、意匠の創作を促し、それによって産業をより発展させることが意匠法の目的だと言えます。
意匠権の発生
ここで注意する点は、意匠権という権利がいつどのように発生するかです。
著作権の場合、著作物が完成したその瞬間に自動的に著作権が創作者に生じますが、意匠権は異なります。意匠権の場合には、特許庁に「意匠登録」の出願をして、それが認められてはじめて創作者に意匠権が付与されます。
意匠登録の審査では、意匠の「新規性」(デザインが今までにない新しいものかどうか)、や「創作非容易性」(デザインが簡単に真似できるものであってはならない)等の審査をクリアすることが必要となります。
加えて、出願料(16000円)と登録料(年8500~16900円)が必要です。
審査を通過して登録料を支払うと、出願した物品に意匠権が発生することになります。
意匠権を維持するためには、毎年登録料を支払って更新する必要がありますが、最大25年間意匠権が保護されます。
ストックフォトと意匠権
意匠登録された物品を写真に撮ってストックフォトで販売可能か
「意匠」とは何か
では「意匠の実施」とは何でしょうか。それを見ていく前にまず、「意匠」とは何かについて確認する必要があります。
意匠法では物品の意匠に関して次のように定義されています:
物品の意匠とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」であり、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」(同法第2条)。
ここで重要な点は、意匠は物品そのものの形や、物品の表面に描かれた模様や色彩が結びついて、それによって美感を生じさせるものと述べられている点です。
つまり、意匠とは、「物品」と切り離されたところで単独に鑑賞される模様や色彩のことではなく、「物品」の形状と模様や色彩は混然一体となりながら「意匠」を形成しているという点です。
「可撓伸縮ホース事件」と呼ばれる、曲げられるホースの意匠の類似性について争われた裁判で、最高裁は昭和49年3月19日の判決で、意匠法第3条1項の意匠の類似性に関する言及の中で、「意匠は物品と一体をなす」ことが確認されています(参照)。
また、特許庁の「意匠審査基準」の第Ⅲ部第1章の2.2でも「意匠は、物品等の形状等であることから、審査官は、物品等自体の形状等と認められないものは、意匠法上の意匠に該当しないと判断する。」として、物品と意匠の不可分性について述べています(参照)。
このように、物品と模様や色彩は切り離すことができない、ということが意匠法の規定する「意匠」の特徴となっているといえます。
「意匠の実施」とは何か
意匠法の目的のところで述べたように、意匠法は第23条で、意匠権者が自分の意匠を「専有」することを認めています。
しかし、意匠法は意匠に係る際限のない権利を意匠権者に認めているわけではありません。
意匠法は「意匠の実施」という言葉を使って、意匠権者が自分の意匠に関して行使できる専有的な権利の範囲を示しています。
意匠法第2条第2項によると、「意匠の実施」とは、「意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸し渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸し渡しの申し出(譲渡又は貸し渡しの展示を含む)をする行為」であることが示され、第23条で意匠権者が「意匠の実施を専有」できることが明記されています。
つまり、意匠権者が自分の意匠に関して専有できる行為は、意匠に係る物品を、製造すること、使用すること、譲渡、貸し渡しをすること、輸出したり輸入したりすること、貸し出しを申し出て展示等を行うことだと理解できます。
ストックフォトとの関連でいえば、意匠登録された物品の写真を撮ってそれをストックフォトとして販売するという行為が、意匠法第23条が意匠権者に与えている「意匠の実施」の「専有」の権利を侵すことになるかということです。
ストックフォトは意匠権を侵害するか
著作物の複製と意匠物の複製の違い
絵画などの著作物の場合、著作物を写真に撮ったりイラストとして描き写すことは(私的な使用と引用での使用を除き)著作物の複製権の侵害にあたります。
ですので、ストックフォトで肖像権と並んで最も気を付けなければならないのが、著作権です。ストックフォトの審査では、著作物が写りこんでいる写真は却下されます。ただし、著作権者に許可をもらえる場合には、プロパティーリリースに著作権者からのサインをもらえばストックフォトとして販売可能となります。
一方、意匠権のある物品の場合には、単にその物品を写真に写したりイラストで書き写すことだけでは、意匠権の侵害にはならないというのが通説となっています(参照)。ただ、注意が必要なのは、例えば一点物の家具などの工芸品のように、その物品が意匠権と同時に、著作権法で認められる美的な要素がある場合です。その場合には、許可なく撮影をすると著作権侵害の可能性が生じます。
意匠物を複製するということ
なぜ、意匠物は写真に撮っただけでは意匠権を侵害したことにならないのでしょうか。
「意匠とは何か」のところで見てきたように、意匠法は「意匠」を物品と一体化されたものと定義付けています。意匠登録の際には、(立体物を正確に平面に表現する)正投影図や3Dのグラフィックデザインによる「図面」の提出が求められます。写真で提出するときにも、すべてにピントが合ったパンフォーカスで、ゆがみのないパースで撮影された正確な六面図が求められます。
意匠物を複製するということは、意匠登録の際に申請された図面をその通りに、もしくは類似させて、物品を立体的に製作することを意味しています。したがって、立体物である意匠物を平面の写真として撮影することは、意匠物を複製したことにも、(すでに見た)意匠法第23条が意匠権者に与えた「意匠の実施」の「専有」を侵害したことにもならならないのです。
物撮り写真のストックフォト審査
したがって、冒頭に掲げたメカニカルペンシルの写真をストックフォトとして販売できるかどうかという問いに対しては、もっぱら意匠法という観点から見た場合には可能であるといえそうです。
ただし、ここまで読んでいただいた方で、すぐにストックフォトの審査に物撮りの写真を提出しようとしている人、少しお待ちください。
もし実際に、冒頭の写真をそのままどこかのストックフォト会社の審査に提出したら、通る可能性と却下される可能性はおそらく半々程度となると思われます。実は、物品の写真をストックフォトで販売するには、意匠法以外にも注意しなければならない法律が存在します。
次回の記事では、実際のストックフォトの審査における、不正競争防止法の扱いを中心に見ていく予定です。